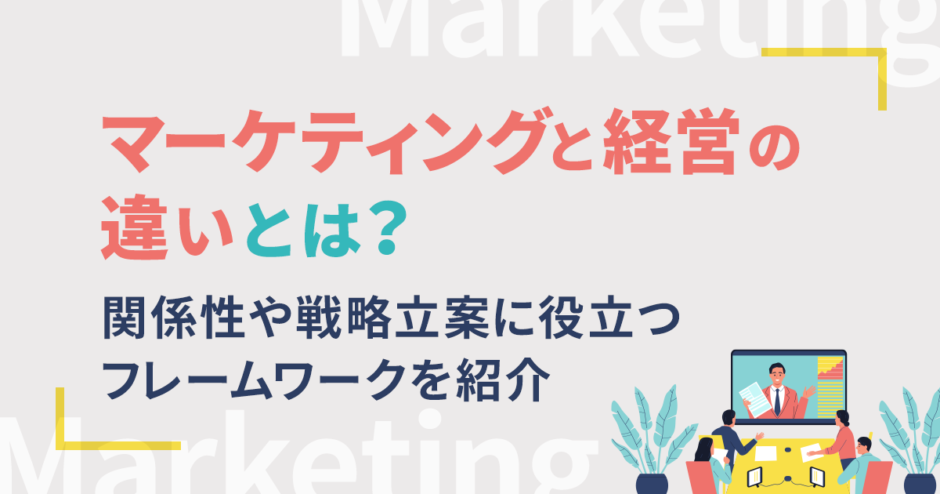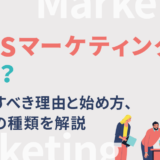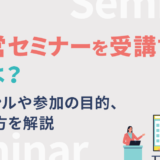マーケティングは経営戦略の一部です。
経営では自社を中心に考えますが、マーケティングでは商品・サービスを中心に戦略を練ります。
マーケティングを実践することで、顧客ニーズを理解でき、経営資源を有効活用できる戦略を立案できます。
この記事では、マーケティングを経営戦略に活用したい人のために、2つの違いと関係性を明確にし、戦略立案に役立つフレームワークを紹介します。
ぜひ自社の戦略を考える際の参考にしてください。
マーケティングと経営の違い
マーケティングは経営の一部門です。
経営戦略を実現する手段や課題解決の中心に、マーケティング戦略が位置づけられています。
マーケティングとは
マーケティングとは、顧客のニーズや市場の動向を把握し、製品やサービスの価値を最大化して顧客に届けるための活動全般です。
誰に・どのような価値を・いくらで・どのように届けるのかを考えます。
マーケティングは商品開発や価格設定、販促、流通など、顧客志向の視点から市場で売れる仕組みを作ります。
顧客の関心やトレンドが変化しやすくなっているので、常に顧客ニーズをつかみ、商品・サービスに反映させる必要があります。
経営とは
経営とは、企業や組織が継続的に存続・発展していくために、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を最適に活用しながら、組織全体をマネジメントする活動です。
事業戦略立案や組織運営、財務管理、人事、リスクマネジメントなど幅広い領域を網羅します。
企業内部だけでなく、顧客や取引先、社会との関わりが不可欠であり、価値の提供や社会課題の解決といった社会的役割も含まれます。
マーケティングが経営戦略に役立つ3つの理由
マーケティングは経営戦略の実効性を高め、企業の成長と競争力強化に不可欠な役割を果たします。
現代のような変化の激しい市場環境では、マーケティングの視点を経営戦略に組み込むことが、持続的な企業価値向上のカギとなります。
1. 顧客ニーズに基づく戦略策定ができる
マーケティングは、市場や消費者の動向、競合他社、自社の状況を客観的に分析する環境分析から始まります。
現代は顧客ニーズが細分化しており、従来のような一律の宣伝だけでは商品やサービスが売れない時代です。
マーケティングによって市場や顧客のニーズを把握できるため、顧客に寄り添った経営戦略を立案できます。
市場の変化に合わせて、PDCAサイクルを回して戦略を継続的に見直すことも重要です。
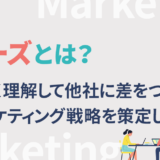 ニーズとは?正しく理解して他社に差をつけるマーケティング戦略を策定しよう
ニーズとは?正しく理解して他社に差をつけるマーケティング戦略を策定しよう
2. 経営資源を最適に配分できる
経営戦略にマーケティングの視点を取り入れることで、ヒト・モノ・カネ・情報といった限られた経営資源を最も効果的に活用でき、無駄なプロモーションやコストを削減しながら収益の最大化を目指せます。
市場分析やターゲティングの結果、伸びしろのある市場に集中して経営資源を投下し、不採算部門への過剰投資を防止できます。
マーケティングの知見や市場データを共有し、サプライチェーンや営業などの他部門とも連携することで、組織全体で無駄な重複業務をカットできるでしょう。
3. 市場変化に柔軟に対応できる
現代のビジネス環境は変化が激しく、不確実性が高いことが特徴です。
企業が持続的に成長し続けるためには、市場の動向や環境の変化をキャッチアップし、必要に応じて戦略の軌道修正を素早く行う能力が不可欠です。
事業展開の複数のシナリオをあらかじめ用意しておけば、不測の事態が起こっても柔軟に対応できます。
マーケティングを実行した結果を分析し、期待通りの成果が出なかった場合には、速やかに経営戦略自体の軌道修正を行いましょう。
マーケティングと経営戦略立案に役立つフレームワーク7選
フレームワークは単独で使うだけでなく複数を組み合わせて活用することで、精度の高いマーケティング戦略や経営戦略の立案が可能になります。
自社の課題や目的に応じて適切なフレームワークを選択し、体系的に戦略を策定することが重要です。
1. 3C分析
3C分析は、顧客(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)の3つの視点から内部・外部環境を整理し、戦略の方向性や差別化ポイントを明確にします。
| 顧客 | 顧客や市場の動向全体を把握 ・市場規模 ・市場の成長性 ・顧客ニーズ ・購買行動 など |
| 競合 | 業界内での自社と競合のポジションを比較 ・同業者や代替サービスの動向 ・競合の強み弱み ・シェア ・差別化ポイント など |
| 自社 | 自社の提供価値の明確化 ・自社の強み弱み ・資金/人材など経営資源 ・現在の商品/サービス など |
3C分析で顧客・競合・自社それぞれの状況を整理することで、成功のための機会や課題、自社が取るべき立ち位置が明らかになります。
2. SWOT分析
SWOT分析は、組織や事業を取り巻く環境を「内部」と「外部」に分け、各環境のポジティブ・ネガティブ要因を整理し、戦略の方向性を明確にするフレームワークです。
| 強み(Strength) | 自社が他社と比べて優れている点 ・コア能力 ・技術 ・ブランド ・リソース など |
| 弱み(Weakness) | 自社が他社と比べて劣っている点 ・自社の課題 ・ボトルネック ・改善が必要なポイント など |
| 機会(Opportunity) | 外部環境の好転要因 ・市場の成長 ・顧客ニーズの変化 ・規制緩和 ・テクノロジー進化 など |
| 脅威(Threat) | 外部環境のリスク要因 ・業界競争激化 ・顧客ニーズ低下 ・法規制強化 ・社会/経済環境の悪化 など |
SWOT分析では自社の強み弱みを明確にした後、外部環境の機会と脅威を抽出します。
4つの象限を組み合わせることで、強みや機会を活かしつつ、弱みや脅威への対応策を検討できます。
- 強み×機会:成長のための攻める戦略策定
- 強み×脅威:強みを活かしたリスク対応策
- 弱み×機会:弱みを克服し機会を活かすための改善策
- 弱み×脅威:守り・撤退・再編戦略の検討
客観的データや根拠に基づき、どの象限に注力すべきか優先順位を明確にすることが重要です。
3. PEST分析
PEST分析は、ビジネス環境の大きな潮流を読み解くためのフレームワークです。
政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)のマクロ環境要因を分析し、外部環境の変化に備えます。
| 政治(Politics) | ・政治体制 ・法律/規制 ・政府政策 ・税制 ・貿易政策 など |
| 経済(Economy) | ・経済成長率 ・景気動向 ・為替/金利 ・雇用情勢 ・消費動向 など |
| 社会(Society) | ・人口構造 ・ライフスタイル ・文化 ・環境意識 ・消費者ニーズ など |
| 技術(Technology) | ・技術革新 ・研究開発 ・知的財産 ・インフラ整備 ・特許政策 など |
4つの切り口ごとに業界や市場全体に影響を与える重要要因をピックアップし、自社や業界への影響をポジティブとネガティブの両面で整理します。
マクロ環境は絶えず変化するため、定点観測と定期的な見直しが重要です。
4. STP分析
STP分析は、市場を細分化してターゲット市場を選定し、自社や商品・サービスの立ち位置を明確化する3つのステップで構成されます。
| セグメンテーション(Segmentation) | 市場の細分化 ・地理的特性(地域、国、都市規模) ・人口統計的特性(年齢、性別、家族構成、所得など) ・心理的特性(価値観、ライフスタイル、性格) ・行動的特性(購買頻度、利用場面、ブランドロイヤルティ) |
| ターゲティング(Targeting) | 有望な顧客層の選定 ・市場規模や成長性 ・自社リソースや強みとの適合度 ・収益性や戦略的な重要性 |
| ポジショニング(Positioning) | 差別化 ・強みの明確化 ・価値提案整理 ・競合比較 ・顧客への位置づけ形成 |
STP分析で「どの市場で」「どの顧客に」「どのような独自価値で」勝負するかを明確にでき、ブレない戦略立案が可能となります。
 ポジショニングはマーケティングに重要!戦略立案の方法や成功事例を解説
ポジショニングはマーケティングに重要!戦略立案の方法や成功事例を解説
5. 4P分析
4P分析は、自社の商品・サービスをどのように市場に提供するかを具体化するフレームワークです。
| 製品(Product) | ・品質 ・デザイン ・機能 ・ブランド ・アフターサービス など |
| 価格(Price) | ・販売価格 ・価格設定戦略 ・割引 ・支払い方法 ・価格帯 など |
| 流通(Place) | ・商品の販売ルート ・流通チャネル ・店舗立地 ・ECサイト ・物流 など |
| プロモーション(Promotion) | ・広告 ・販促活動 ・SNS ・営業 ・口コミ など |
4P分析で各要素をバランスよく組み合わせることで、製品・サービスが売れる仕組みを設計できます。
6. 4C分析
4C分析は、顧客視点でマーケティング戦略を組み立てる際に活用します。
4P分析が企業視点で設計するのに対し、4C分析は顧客視点から戦略を組み立てます。
| 顧客価値(Customer Value) | ・ベネフィット ・満足度 |
| コスト(Cost) | ・金銭的負担 ・時間 ・手間 |
| 利便性(Convenience) | ・アクセスのしやすさ ・購入や体験の簡便さ |
| コミュニケーション(Communication) | ・双方向の情報発信 ・信頼構築 |
4C分析は顧客が感じる価値を最大化するためのアプローチを検討するためのフレームワークです。
近年はデジタル化の進展や顧客とのダイレクトな関係構築が重視されることから、4C分析の重要性が増しています。
7. 5フォース分析
5フォース分析は、業界構造の収益性や競争環境を5つの競争要因(フォース)に分けて評価し、自社や事業が置かれているポジションの本質的な強み・弱み・リスク・チャンスを明確化する手法です。
| 業界内の競争 | 既存の競合企業同士による競争の激しさ |
| 新規参入の脅威 | 新しい企業が業界に参入しやすいかどうか、参入後の影響 |
| 代替品の脅威 | 同じニーズを満たす他業界・他製品による置き換えリスク |
| 買い手の交渉力 | 顧客が価格や条件面でどれだけ力を持っているか |
| 売り手の交渉力 | 仕入先が価格や条件面でどれだけ力を持っているか |
5フォース分析では、5つの力のバランスや強さの評価により、どの業界が高収益になりやすいか、どの脅威への対策が不可欠かを把握します。
自社単体でなく業界全体の競争構造を分析する視点を持つことが重要です。
 競合調査を進める方法は?調査項目やフレームワークも解説
競合調査を進める方法は?調査項目やフレームワークも解説
マーケティングをうまく活用して経営戦略を実践しよう
企業が持続的な成長を実現するためには、マーケティングを経営戦略に組み込むことが不可欠です。
マーケティングは、顧客ニーズや市場環境の変化を捉え、自社の強みと結び付けて価値を提供する仕組みを構築します。
マーケティングを活用することで商品やサービスが市場で選ばれ続ける基盤を設計でき、経営資源を効果的に配分できるようになるでしょう。

「自己流で集客してしまっていて、この先が不安…」
「売上アップに繋がる確実な方法が知りたい」
と感じていませんか?
事業を大きく成長させたくても、売上が安定しないことに悩む経営者は多くいらっしゃいます。
実は、安定した売上に必要なものは
誰もが知っているようなネームバリューでも多額の広告予算でもありません。
それが、お客さまに選ばれ続ける「本質的なマーケティング」
一度本質的なマーケティングを手に入れれば
中小企業でも、予算が少なくても、あなたのビジネスの売上をずっと伸ばし続けることができます。
では、本質的なマーケティングとは一体どうすれば実践できるのか?
それを「三方よし」マーケティング特別セミナーでお伝えしています。
業界後発から20年で売上1,600億円を達成した
湘南美容クリニック 相川代表をはじめ
5万人以上の経営者・個人事業主が受講し
飛躍的な成長を手にしている講座です。
・集客に苦戦している
・早く成果につなげたい
・売上を安定させたい
という方は、席に限りがございますので
まずはこちらの無料体験セミナーにご参加ください。
FAQ・よくある質問
マーケティングと経営の違いは?
マーケティングは経営の一部門です。
経営戦略を実現する手段や課題解決の中心に、マーケティング戦略が位置づけられています。
マーケティングが経営戦略に役立つ理由は?
マーケティングは経営戦略の実効性を高め、企業の成長と競争力強化に不可欠な役割を果たすからです。
現代のような変化の激しい市場環境では、マーケティングの視点を経営戦略に組み込むことが、持続的な企業価値向上のカギとなります。
#マーケティング経営
 コラム
コラム